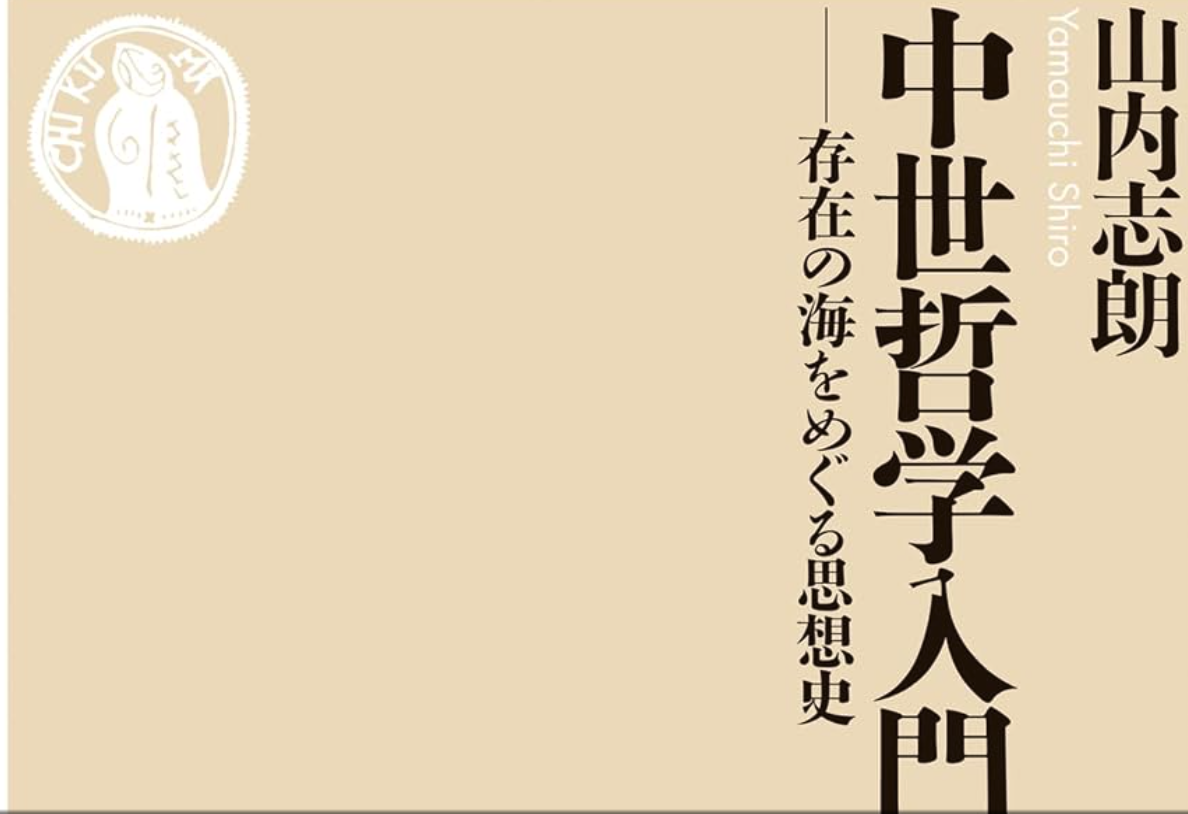唯名論は普遍を名のみのものと捉えた
— 未熟なリバタリアンがAIソクラテスと思考実験してみた (@bluesbookblog) October 1, 2025
ダマスケヌスの本質とは実体の無限で無際限の海のごときものである
→
スコトゥスのこのもの性は個体を成立させる個体的な存在実質とは種に対応する規定性に付与される度・強度である
→
オッカムの唯名論は固体化の原理は不要であるhttps://t.co/ya3KFqFr6C
普遍をめぐる三つの看板
— 未熟なリバタリアンがAIソクラテスと思考実験してみた (@bluesbookblog) October 1, 2025
オッカム「知性の外部に存在するものはいかなるものも普遍ではない」
スコトゥス「普遍は事物の本性の内にある」
トマスとヘルウェウス「知性の外部に普遍的事物は基本的にあるが、こうした普遍的事物の一性は、理虚的一性であって実在的一性ではない」https://t.co/ya3KFqFr6C
AIソクラテスと思考実験してみた
Q1: 唯名論は個体性をどう説明できる?
唯名論では個体性を特別な「固体化の原理」によって説明する必要はなく、名前や言語を通じた区別で十分と考える。根拠はウィリアム・オッカムの思想で、彼は「普遍は存在しない、あるのは個体だけ」と主張した。例えば「犬」という言葉は犬そのものの実在ではなく、人間が似た特徴を持つ個体群を便宜的にまとめた呼び名にすぎない。だから差異は各個体の経験や知覚から説明可能で、余分な本質や形相を持ち込む必要がないとされる。
Q2: 相対主義と絶対主義の歴史はどう続いてきた?
人類の思想史は相対主義と絶対主義の往復として整理できる。古代ギリシャではソフィストが相対主義を唱え、ソクラテスやプラトンがイデア論で絶対的真理を追求した。次に原子論者デモクリトスが相対的な物質観を示し、アリストテレスが本質論で体系化した。中世に入ると唯名論が相対的立場を代表し、実在論が普遍の存在を主張した。つまり対立の形は変わっても、「真理は人に依存するか、それとも人を超えて存在するか」という問いが常に繰り返されてきた。
Q3: 陰謀論と科学も相対主義vs絶対主義?
陰謀論と科学の対立も相対主義と絶対主義の構図に重ねられる。科学は再現性と検証可能性を前提とし、客観的な真理を目指す絶対主義的性格を持つ。一方、陰謀論は個人の解釈や疑念を優先し、真偽を相対的に扱うため反証が困難になる。例えばワクチン陰謀論は、どんなデータを提示しても「政府が隠している」という主張にすり替えられ、証拠の基準が揺らぐ。したがって民主主義における公共議論は、相対主義が広がると脆弱になりやすい。
Q4: 経験論と合理論の現代的な争点は?
経験論と合理論はAI研究や言語学で再燃している。チョムスキーの「刺激の貧困論」は合理論を代表し、人間の言語能力には生得的な制約があると主張した。一方、ベイズ統計や大規模言語モデルの成功は、経験論の「大量のデータから学習できる」という立場を後押ししている。経験論は脳の再現や悪魔の証明が必要で不利とされてきたが、計算機技術の進歩により再び可能性が広がっている。つまりAIは両者のバランスを再検討させる舞台となっている。
Q5: どちらの立場が社会的信頼を得やすい?
合理論の方が社会的に信頼を得やすい。理由は立証の容易さにある。例えば「言語獲得には生得的制約がある」という主張は一つの事例で証明できるが、「制約が全くない」と示すのは悪魔の証明に近く不可能に近い。さらに合理論は哲学や論理学の伝統と結びつきやすく、権威を持ちやすい。逆に経験論は証拠の量や計算能力に依存するため、時代や技術に左右されやすい。この非対称性が、合理論が優位に見える背景となっている。
Q6: ルネサンスはどのように学芸運動から生まれた?
ルネサンスは学芸運動から生まれた。14世紀以降、大学では神学部で実在論を、学芸学部で唯名論を学ぶ対立があった。オッカムの唯名論は反教皇の立場と結びつき、権威への批判精神を広めた。さらに古典教育を重視する人文主義が芽生え、人間の尊厳や価値を重視する潮流となった。ダンテやエラスムスの著作がその典型例である。こうしてスコラ哲学中心の世界観に対抗し、文化と芸術の復興へとつながったのがルネサンスであった。
Q7: AIは現代の学芸運動になり得る?
AIは現代における学芸運動となる可能性がある。理由は既存の権威構造を揺るがし、新しい価値観を創出する力を持つからだ。ルネサンス期に人文主義が宗教的権威に対抗したように、AIは既得権益や情報独占を崩すツールとなり得る。例えばYouTubeやSNSを通じて一般市民が発信力を得ている現象は、中世の学芸学部が新しい教育を広めた動きと重なる。ただしAIの場合、まず経済や労働への影響が強く、文化変革より先に格差問題を引き起こす可能性が高い。
Q8: 哲学が流行する時代の条件は?
哲学が流行する時代には三つの条件が重なる。第一に物質的な豊かさがあり、人々が生活の基盤を確保できていること。第二に異質な価値観が混在し、既存の秩序が揺らいでいること。第三に現状への停滞感や危機感が強まり、新しい答えを求める状況である。中世のスコラ哲学やルネサンス期の人文主義も、この三条件が背景にあった。現代社会もグローバル化による多様な価値観と経済不安を抱えており、哲学的議論が再び注目されやすい環境にある。
Q9: 現代で影響力を持つ哲学分野は?
現代で最も影響力を持つのは政治哲学だ。理由は民主主義の制度が揺らいでいるからである。20世紀前半にラジオを駆使して権力を握った独裁者がいたように、今日の政治家はAIやYouTubeなどのプラットフォームを利用しやすくなっている。普遍論争が「概念は実在するか」という問いだったのに対し、現代の論点は「公共性や民主主義は実在するか」という抽象的価値の所在にある。したがって、国民と政治の関係を問い直す政治哲学が中心に立っている。
Q10: 批判と揶揄の境界をどうルール化する?
批判と揶揄の境界は「対象が行為や主張か、それとも人格や属性か」で区別でき、これをルール化し監視するモデルが必要となる。具体的には①主張に根拠を伴う場合は批判、②人格攻撃や蔑称を含む場合は揶揄と判定する。AIモデルを使えば記事内の侮蔑語や根拠リンクの有無を自動検出でき、人手審査と組み合わせて運用可能だ。例えば「○○の政策は失敗」と述べれば批判だが、「○○は無能」と書けば揶揄になる。この基準で公共的議論を守れる。
あなたも読書を始めよう
・自分が最大の資本であり、最大の投資先になる
・今が人生で一番若く、早く始めるほど複利が働く
・本は信憑性があり、読書は能動的ため成長できる