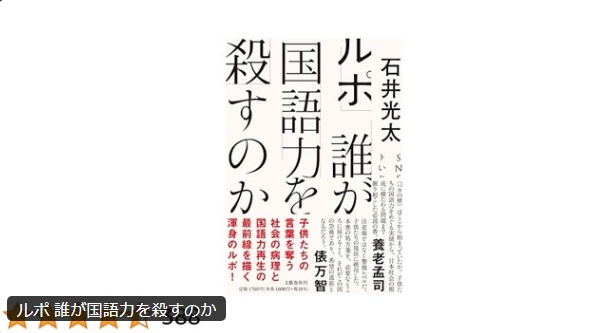- 概要
- 著者
- 家庭が国語力を殺している
- 教育が国語力を殺している
- 国語力の低さが悪循環する
- AIと思考実験してみた
- Q1: 「誰が国語力を殺すのか」という本の内容について、どのように感じましたか?
- Q2: 具体的に、どのような言葉が不足していると感じますか?
- Q3: ゲームやネットのコミュニケーションと実生活のコミュニケーションでは、どんな違いがあると思いますか?
- Q4: こうした傾向が続くと、長期的にどんな影響があると思いますか?
- Q5: そうした分断が進むと、社会にはどんな変化が起こると考えますか?
- Q6: そうした状況を防ぐために、家庭や教育でどんな取り組みができると思いますか?
- Q7: 遊びながら言葉や想像力を育てるには、どんな方法が有効だと思いますか?
- Q8: こうした取り組みを社会全体に広めるには、どんな工夫が必要だと思いますか?
- Q9: 具体的に、どんな制度が効果的だと思いますか?
- Q10: こうした施策を成功させるには、どんな課題があると思いますか?
概要
子供たちの言葉を奪う社会の病理と国語力再生の最前線を描く渾身のルポ!
著者
石井光太
1977年東京生まれ。作家。国内外の貧困、災害、事件などをテーマに取材・執筆活動をおこなう。2021年『こどもホスピスの奇跡 短い人生の「最期」をつくる』で新潮ドキュメント賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
家庭が国語力を殺している
家庭が国語力を殺している
— ひろき@AIと思考実験してみた (@bluesbookblog) February 15, 2025
コミュニケーション不足になっている
国語力は語彙力と情緒力、想像力、論理的思考力、表現力がある
12歳までに2万語を覚え、日常で使う3000語を身に付けていたが
共働きやネット、ゲームの影響で基礎となる語彙が身に付いていない
読書します!https://t.co/lIzqjcyoSE
教育が国語力を殺している
教育が国語力を殺している
— ひろき@AIと思考実験してみた (@bluesbookblog) February 16, 2025
国語力が不要な構造になっている
国語力は語彙力と情緒力、想像力、論理的思考力、表現力がある
学校や受験で知識の暗記や正論を述べることが捉われ、そこから自分の言葉で考える、想像する、表現することができなくなっている
読書します!https://t.co/lIzqjcxR36
国語力の低さが悪循環する
国語力の低さが悪循環する
— ひろき@AIと思考実験してみた (@bluesbookblog) February 16, 2025
論理的に考えられず問題に繋がる
対面は感じる→相手の気持ちを想像する→言葉を整理する→発言するだが
ネットは感じる→発言するのため、直接的な短い単語に触れ過ぎ、言葉をまとまりで理解できず、場当たり的なストレス発散になる
読書します!https://t.co/lIzqjcyoSE
AIと思考実験してみた
Q1: 「誰が国語力を殺すのか」という本の内容について、どのように感じましたか?
この本では、家庭が国語力を殺しているという指摘がされていて、共働きやネットゲームの影響で子どもたちが十分な語彙力を身につけられていないという問題を扱っていました。もともと12歳までに2万5千語を覚え、日常で3千語を使うと言われていましたが、現代の子どもたちはその基礎的な言葉を習得できていない。特に、国語力には「語彙力」「情緒力」「想像力」「論理的思考力」「表現力」が含まれるけれど、それらが十分に育たないまま大人になってしまう危機があると感じました。
Q2: 具体的に、どのような言葉が不足していると感じますか?
日常生活、学校、そして将来的にビジネスの場で必要な言葉が不足していると思います。例えば、先生や上司との適切な受け答え、頼みごとや謝罪の仕方、説得力のある意見の伝え方などですね。今の子どもたちは、限られたコミュニケーション環境でしか会話していないため、知らない人との会話や対話のスキルが育ちにくくなっている気がします。特に、ゲームの世界では、リアルな対面コミュニケーションの要素が少なく、ネット特有の短縮された言葉や感情的な言葉ばかりに触れてしまうため、論理的に整理して話す能力が弱くなってしまうのかもしれません。
Q3: ゲームやネットのコミュニケーションと実生活のコミュニケーションでは、どんな違いがあると思いますか?
本の中で指摘されていたのは、ネットやゲームのやり取りでは、相手の気持ちを想像して言葉を整理するプロセスが省略されてしまうことです。リアルな会話では、「相手の表情を見る → 気持ちを想像する → 言葉を選ぶ → 発言する」という流れがありますが、ネットでは「発言する」だけが先行し、深く考えるプロセスが抜け落ちがちです。結果として、短く直接的な表現ばかり使うようになり、まとまりのある言葉を理解したり、適切な表現を選んだりする力が弱くなってしまう。それが、場当たり的なストレス発散のような発言の増加にもつながっているのかもしれません。
Q4: こうした傾向が続くと、長期的にどんな影響があると思いますか?
長期的には、ビジネスの場などで知らない人と適切に話す能力が欠けていくと思います。驚いたのは、最近ではインターホンを押したり、知らない人に電話をかけることができない子どもが増えているという話です。昔は友達と遊ぶために勇気を出してインターホンを押したり、電話をしたりしていたのに、今では個別に直接アクセスできる手段があるため、そうした経験が少なくなっている。これが積み重なると、社会に出ても対面でのコミュニケーションが苦手になり、結果的に人との接触を避ける傾向が強まる。そうすると、分断が進み、ますます対話ができない社会になってしまうのではないかと感じます。
Q5: そうした分断が進むと、社会にはどんな変化が起こると考えますか?
分断が進むことで、人々がそれぞれの価値観の中で棲み分けをし、異なる意見に触れにくくなると思います。その結果、陰謀論が入り込みやすくなり、異なる考えを持つ人たちを否定する風潮が強まる。また、ネット上では会話ではなく過激な発言が増え、便乗や炎上の文化が加速してしまうかもしれません。こうなると、まともな議論や対話が成り立たず、ますます価値観の対立が激しくなる。結果として、社会全体が分断され、お互いの理解がどんどん難しくなっていくのではないかと思います。
Q6: そうした状況を防ぐために、家庭や教育でどんな取り組みができると思いますか?
まず、家庭では子どもとしっかり話すことが大事だと思います。昔に比べて親子で一緒に遊ぶ時間が減っているのではないかと感じます。また、学校教育では知識の暗記や点数を取ることばかりが重視され、自分の言葉で考えたり、想像力を働かせたり、表現したりする機会が少なくなっている。このままでは、主体的に考える力が育ちにくい。だからこそ、家庭では一緒に食事をし、自然と会話が生まれる場を作ることが大切だと思います。
Q7: 遊びながら言葉や想像力を育てるには、どんな方法が有効だと思いますか?
1つは、親子でしりとりや即興ストーリー作りなど、言葉を使う遊びを増やすことです。私の経験では、車の中でしりとりをしていたとき、普通のしりとりに飽きたら「頭文字を取ったしりとり」など、新しいルールを考えていました。こうした工夫が創造力や発想力を育むと思います。また、旅行中にタブレットを使うのではなく、家族全員が同じ体験を共有することも大切だと思います。
Q8: こうした取り組みを社会全体に広めるには、どんな工夫が必要だと思いますか?
政府が積極的に関与し、家庭での会話を増やす仕組みを作るべきだと思います。例えば、「ノーデジタルデー」を作り、スマホを使わない日を推奨する。あるいは、企業が「ファミリータイム」を奨励し、早く帰宅できる日を作ることで、家庭のコミュニケーションを増やす。こうした社会全体の動きがないと、個々の家庭だけでは解決が難しい問題だと思います。
Q9: 具体的に、どんな制度が効果的だと思いますか?
1つは「ノーデジタルデー」を企業や政府が推奨し、実施した家庭にはポイントや割引などのインセンティブを与える制度です。2つ目は、学校での対話型授業をもっと増やし、子どもたちが自分の言葉で考える機会を持てるようにする。3つ目は、SNSリテラシー教育を義務化し、ネットの影響を理解する力を育てること。こうした取り組みを加速させることが必要だと思います。
Q10: こうした施策を成功させるには、どんな課題があると思いますか?
家庭に負担をかけすぎず、自然に取り組めるような工夫が必要だと思います。また、社会全体で「会話の重要性」を共有しないと、子どもが学校で話題にしたときに馬鹿にされるような風潮を変えられない。だからこそ、個人ではなく社会全体で取り組める制度が求められると思います。
あなたも読書を始めよう
・自分が最大の資本であり、最大の投資先になる
・今が人生で一番若く、早く始めるほど複利が働く
・本は信憑性があり、読書は能動的ため成長できる